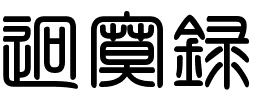前回書いた「論争」のまとめに歴史社会学者の井上義和氏のコメントがあったことから氏の著書(共著)である『「知覧」の誕生』を手に取りました。
この本では、戦後しばらくは顧みる者もなくただ茶畑が広がっていた知覧の飛行場跡が次第に「特攻戦跡」となっていく過程が考証されています。注目すべきは「特攻とはどのようなものであったか」ではなく、戦後の「戦跡化」に焦点が当てられていることです。
他にも、「朝鮮人特攻隊員のイメージの変容」や、「戦闘機」に執着するミリタリー・ファンの存在など、10人の若手学者による考察が興味深い切り口で行われています。
詳しい内容は実際に本を手にとって読んで頂くとして、ここでは個人的に引っかかった部分を挙げておきます。
特攻隊員たちは、戦争状態のなかで敵を殺す任務を担ったという意味で、加害者としての側面を有していた。それと同時に、必ずしも自ら望んだとはいえない自爆攻撃を受け入れざるをえなかったという意味では、被害者でもあった。しかし、この加害と被害の両義性は……(後略)
本書の中では数少ない、特攻それ自体に言及した部分(79ページ、第二章「〈平和の象徴〉になった特攻」より、執筆は山本昭宏氏)ですが、俄に首肯しがたいものがあります。
「加害者でもあり被害者でもある」という言い方は、「AがBに対して、またBがAに対して互いに加害者であり被害者でもある」という場合に使うのが普通ですが、上では、「A(特攻隊員)はB(敵)に対して加害者であり、同時にC(特攻を命じた上官)に対して被害者である」というように主体が三つあり、それぞれの加害性及び被害性は程度も性質も異なります。
更に言えば、国際法上、戦時下にあっては正規軍の将兵が敵を殺害しても罪に問われることはありません。なるほど、上で言う「加害」とは罪に問われるか否かとは別の話でしょうが、そうだとしても、敵に対する加害者性は戦争である以上全ての将兵が有するものであり、特攻隊員固有のものではありません。敵にとっては爆弾や魚雷で攻撃されようと体当たりであろうと同じ「害」であるはずです。
ごく広い意味での「両義性」があるのは確かですが、特攻隊員の「加害性」に注目することに意味があるとは思えません。
—
本書の語り口は実証的、分析的で、決して右傾化を糾弾するといった内容ではありません。しかし、それでも幾分かは特攻の美化への危惧が見て取れます。確かに、隊員の遺書を読み、生き残った人の話を聞くなど、特攻とは何だったのかを知ろうとすればするほど「至誠に心うたれる」というような、美化してしまう「力学」が働くような気がします。
もう少し考えを深める必要がありそうです。