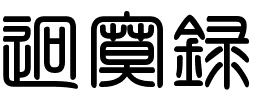ずいぶん久しぶりの更新です。
最近、中野信子さんの「 努力不要論」を読みました。副題には「脳科学が解く!「がんばってるのに報われない」と思ったら読む本」とあります。私の信念とは真っ向から異なるので、いったいどのような内容なのか興味がわきました。
読み終わってみると、結局のところ「無駄な努力」や「他人に押し付けられた努力」はやめようということのようです。言い換えれば「自ら望んでする合理的な努力」はどんどんやるべきとのことです。刺激的なタイトルの割には穏当な主張ですね。
さて、同書の中でも引用されていましたが、今から10年前、爲末大さんの以下のようなツイートが話題になったことがあります。
成功者が語る事は、結果を出した事に理由付けしているというのが半分ぐらいだと思う。アスリートもまずその体に生まれるかどうかが99%。そして選ばれた人たちが努力を語る。やればできると成功者は言うけれど、できる体に生まれる事が大前提。
— 爲末大 Dai Tamesue (@daijapan) October 21, 2013
なるほど、「成功者」の定義がオリンピックでメダルを獲得するレベルのアスリートということなら、爲末さんの言うとおりでしょう。しかし、私の考える成功とは必ずしもそういうことに限りません。
部活でレギュラーになる。市民マラソンに参加して完走する。資格試験に合格する。好きな人と結婚する。子供を幸せにする。
これらも立派な人生の目標です。何もノーベル賞を受賞したり、オリンピックで金メダルをとることだけが有意義な人生で、それ以外は無意味だとは思いません。
そして、これらを成し遂げるには何ほどか努力が必要なのです。
努力は不要と言う人々
昨今、「努力など不要」あるいはさらに進んで「努力などすべきではない」といった言説が流行ります。
彼ら曰く、「我々凡人がいくら努力してもイチローや大谷のようにはなれない。だから努力など無意味なのだ」と。これについては既に反論しました。確かにそのような大それた目標に対しては努力は殆ど無意味ですが、我々庶民が抱くささやかな夢を叶えるには努力は依然として有効であり、且つ必要です。
また、ブラック企業でこき使われている人などを例に「努力しても報われることはない」と言う人もいます。しかし、努力と忍従は違います。努力とは他人に強制されてやるようなことではないし、不当な扱いを受けているのであればそこから抜け出す(あるいは戦う)努力をすべきです。私に言わせれば、これこそ努力が必要な場面であって、努力不要論の根拠にはなりません。
なぜこれほどまでに努力を嫌う人が多いのでしょうか。
一つには「努力」という言葉の捉え方の違いがあります。ある人は「努力とは苦痛に耐える事」だと思っている。またある人は「努力とは欲しいものを我慢すること」だと思っている。これらも努力の一側面ではありますが、本質ではありません。
もう一つは、『山月記』の李徴のように、努力してなお世間に認められないことを恐れる心理です。努力していないうちは「俺はやればできる」と言っていられたものが、下手に努力してダメだったときは「やってもできない」になってしまう。つまり、自分の無能さを証明することになってしまう。確かに辛いことですが、ちっぽけなプライドを守るために何もしないのは一番やってはいけないことです。
「偽りの努力」をしてしまう人も多くいます。本当にやらなければいけないことを放っておいて、やらなくてもいいことを一生懸命やる。逃避のための努力は本当の努力ではありません。
努力とは
私は、努力とは「理想を叶えるための合理的な行動」であると思っています。さらに言うと、それは単に目標を達成するために必要なだけでなく、己の矜持を保つために必要なのです。
無論、簡単なことではありません。まず、理想が見つからない。何かおぼろげな理想があったとしてもなかなか形にならないものです。
それでも理想は持つべきだし、それに向かって努力すべきです。なぜなら、それこそが幸福の条件だからです。考えてもみてください、望むものは全て与えられる人生があったとして、それだけで幸福と言えるでしょうか。本人は何の努力もしていない。賢くもない。周囲は腹の中では軽蔑している。そんな裸の王様のような境遇は私なら真っ平です。
やはり人生に努力は必要というのが私の結論です。